
来週上棟を予定している松本市F様邸現場にて、 基礎の中の水を汲みだしてきました! 実用的なダイエットです(笑)
ランニングマシーンで汗水垂らすのもよいのですが、 せっかくですから、何かしら役に立つことをして汗したほうが有益なのではないかと・・・。一挙両得的な思考を持つしおはらです。
5~10cm程は溜まっていたでしょうか。この時期コンクリートは急激に乾燥させたくありませんので、水が張られている方が将来的にいい感じで強度が出ます♪
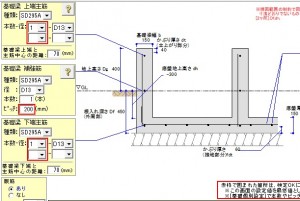
ところでこの基礎はけっこう壁面が高いですね。
でもこれが「べた基礎」の原型なのです。
べた基礎は建物の荷重を全面で受け止めようとするもの。
地面に直接ベタっとコンクリートの平板を置き、その上に建物を載せ、その荷重を分散させようとしているわけです。
このコンクリートの平板を”底盤”(ていばん。ベースとも呼ばれる)といいます。
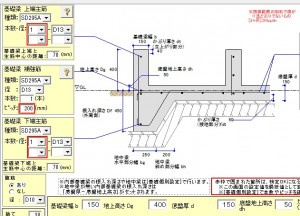
しかしながら一般的には左図のようなべた基礎が主流です。
いったいどっちが正解?
構造計算上はどちらもべた基礎として扱われます。
前述の単純形のものは、よく見ると地盤面(G.L.=ジーエル=グラインドラインの略)よりも中(床下)のほうが低いですね。
気を付けないと、床下内に水が溜まってしまいますので一般化していません。
私は、もともとの土地が低く、地盤面をもっと上げたい場合や、 表面の土が腐葉土などで、いったん取り除くべき場合などに、 この”総掘りべた基礎”(そうぼりべたきそ)の採用を検討します。

総掘りべた基礎の場合、必然的に壁のH寸法が大きくなり、床下点検のための人通口でくり抜かれたとしても、 その下に一部壁が残り、べた基礎の底盤が変形しにくくなります。
この敷地には以前建物が建っていましたが、道路から40~100cm程低い地盤でした。 ですから大雨の際には床下に雨水が回り込んでくることが多く、今度建てるならばぜひ地盤面(G.L.)を上げたいと考えていました。

「木の壁はすぐ腐る。」
そんな都市伝説を打ち破るべく、 軒ゼロ板壁で証明してみたいと思います。
先ほど新潟・山形で震度6強の地震がありました。
心配です。
建て方をやっている最中に震度6強なんかが来たら、どしよ( ゚Д゚)
2019.6.18 Reborn塩原
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ブログを読んでいただきありがとうございます。
Rebornがつくりだす家→施工事例
動画も多数配信中→YouTube『Rebornチャンネル』
お客様の声→暮らしのことば
不動産サイト→不動産“腐”動産にしない!させない ‼」
Instagram毎日更新中→reborn_house_
適宜更新中です。ぜひ、こちらもご覧になってみてください。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
















